 | コンクリートの壁の結露対策 | |
はじめに
冬場はコンクリートの壁などに発生する結露が気になるものです。結露はこまめに拭くのも大変ですし、カビも発生しやすくなります。そこで今回はなぜコンクリートの壁に結露が発生するのかを解説し、さらに結露を予防するための対策と、結露によりカビが発生した場合のカビ取りの仕方についても解説します。
なぜコンクリートの壁に結露が発生するのか
もともと空気中には水分が含まれています。この含められる水分の量というのは限りがあり、気温が下がるほど含んでいられる水分の量も少なくなります。結露は空気が冷たいコンクリートに接触すると、急激に冷やされ、含んでいられる水分の量も減り、その結果あふれた水分が結露となって壁に付着するのです。
同じような現象は外気と接触する窓やサッシでも見られます。どちらも空気よりも熱伝導率が高いので冬場などは急激に冷やされ、そこに空気が接触するとコンクリートの時と同様に結露が発生します。
同じような現象は外気と接触する窓やサッシでも見られます。どちらも空気よりも熱伝導率が高いので冬場などは急激に冷やされ、そこに空気が接触するとコンクリートの時と同様に結露が発生します。
コンクリートの結露を予防するには
断熱シートを張る
ではコンクリートの結露を予防するにはどうすればいいのでしょうか。それには空気を冷たいコンクリートに直接接触しないようにすればいいのです。そのために断熱シートを使います。断熱シートをコンクリートに張ることで直接空気をコンクリートに触れさせないようにすることができます。さらに断熱シートなので断熱シート表面もコンクリートほど冷たくありません。断熱シートを張るときは外周をしっかりと両面テープなどで張り、隙間を開けないようにすることです。断熱シートがない場合は引っ越しの際の梱包などで使うエアキャップ(プチプチ)でも構いません。ただしエアキャップは凹凸があるのでその隙間に結露が発生しやすいです。できれば凹凸のないものの方がいいです。
|
PR ニトムズ 窓ガラス断熱シートフォーム2P E1600ニトムズ amazonで購入 楽天市場で購入 |
石油ヒーターの使用を控える
石油ヒーターは燃費などの面でエアコンよりも安いこともあり、使われる機会も多いですが、部屋の湿度の上昇にもつながります。湿度が高いとそれだけ結露も発生しやすくなります。石油ファンヒーターは1リットルの石油を消費すると、1リットルの水蒸気が発生します。燃費は多少は高くはつきますが、結露が気になるなら石油ファンヒーターではなく、エアコンなどを使うようにしましょう。乾燥が気になる場合は除湿器も併用される方もいるかと思いますが、除湿器の使い過ぎにより部屋の湿度が高くなりすぎると結露も発生しやすくなります。こちらも使いすぎには注意しましょう。
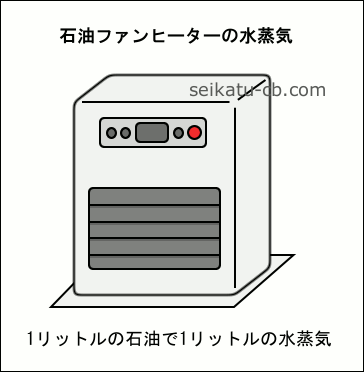
部屋の換気
冬場は外の空気は乾燥している一方で、室内は温かく外に比べて湿度も高いです。そこで定期的に2か所の窓を開けて風の通り道をつくり、部屋を喚起することで、部屋の湿度を下げることができます。また途中で扇風機などを置いて送風すればさらに喚起効果は高まります。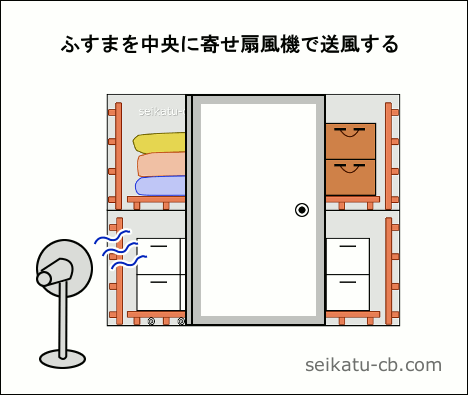
カビが発生した場合は
カビが発生しやすい環境は?
カビは栄養となるちりやほこり、汚れなどがあり、湿度が70〜95%で温度が20〜30度の時に特に繁殖しやすくなります。コンクリートの壁に結露が発生し、室温も上昇して、部屋の中のちりやほこりなども吸着と、カビが生えやすい条件がそろってしまうと、カビが発生してしまうわけです。
カビ取り剤でカビを取る
結露によりコンクリートの壁に黒い斑点のカビが発生することがあります。カビは拭き掃除だけではなかなか落とせないのでカビ取り剤を使います。まずは固く絞った雑巾でカビをふき取り、そのあとカビ取り剤を添付して30分ほど置いておきます。後は水を絞った雑巾でカビとカビ取り剤をよく拭きとります。完全に取り切るのは難しいかもしれませんが、何度かこの作業を繰り返すと目立たなくすることはできます。最後は半日をほどしっかり換気をして乾燥させます。また作業中も換気はしっかりとしておきましょう。
洗濯用漂白剤でもいい
カビ取り剤は洗濯用漂白剤と同じ成分なので、注意を守ればそれほど危険なものでもありません。カビ取り剤がなければ洗濯用漂白剤を使ってもいいです。ただし人の皮膚はアルカリには弱いので使うときはゴム手袋をして作業しましょう。
※ 参考文献
科学的に正しい暮らしのコツ
住まい・汚れスッキリ解消術
科学的に正しい暮らしのコツ
住まい・汚れスッキリ解消術
| 公開日 2018/01/18 |
 TOPへ TOPへ  住まいTOPへ 住まいTOPへ  HOMEへ HOMEへ
|
修繕編一覧
湿気編一覧
その他一覧
ねじが抜けない時
重なったコップの外し方
鏡が曇る原因と対策、洗面所やお風呂場の鏡を曇らせなくするには?
鏡は夏よりも冬に曇りやすいのはなぜ?寒いと表面張力が高くなるのが原因だった!
シールの上手な剥がし方
ガムテープ跡の取り方、はがし方
セロテープ跡の綺麗な取り方、はがし方
油性マジックの落書き
重なったコップの外し方
鏡が曇る原因と対策、洗面所やお風呂場の鏡を曇らせなくするには?
鏡は夏よりも冬に曇りやすいのはなぜ?寒いと表面張力が高くなるのが原因だった!
シールの上手な剥がし方
ガムテープ跡の取り方、はがし方
セロテープ跡の綺麗な取り方、はがし方
油性マジックの落書き
PR |
since 2002/09/28
Copyright(C)2002 生活知恵袋 All Rights Reserved
Copyright(C)2002 生活知恵袋 All Rights Reserved



