 | 押し入れの湿気対策 | |
はじめに
押し入れは湿気がこもりやすい場所で、湿気がたまるとカビや結露などが発生し、衣類や布団などの収納物も傷めてしまいます。そこでここではスノコや新聞紙、除湿剤などを使った押し入れの湿気対策の方法を紹介します。さらに押し入れに湿気を貯めないようにする工夫や、湿気によりカビが発生した場合の対処法についても見ていきます。
スノコを敷く
スノコを敷くと空気の通り道ができて通風がよくなります。湿気は上よりも下のほうにたまるので下に引くスノコは大事です。スノコは下だけに引くものだと思われがちですが、横にもたて置くことで空気の通り道を確保でき、押入れ全体の通風効果も上がります。
奥にスノコを立てかけても構いませんが、収納物をつめすぎないように奥を5cmほどあけて収納すれば、スペースは確保できるのでスノコをわざわざ立てかけなくても大丈夫です。横も隙間を確保できるならあえてスノコを置かなくても問題ありません。床だけはスノコを敷かないとスペースは確保できないので必ず敷くようにしましょう。
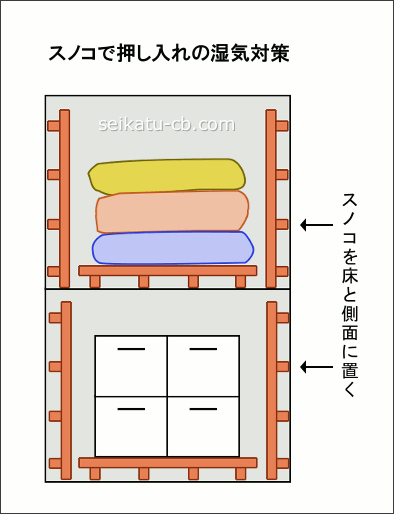
奥にスノコを立てかけても構いませんが、収納物をつめすぎないように奥を5cmほどあけて収納すれば、スペースは確保できるのでスノコをわざわざ立てかけなくても大丈夫です。横も隙間を確保できるならあえてスノコを置かなくても問題ありません。床だけはスノコを敷かないとスペースは確保できないので必ず敷くようにしましょう。
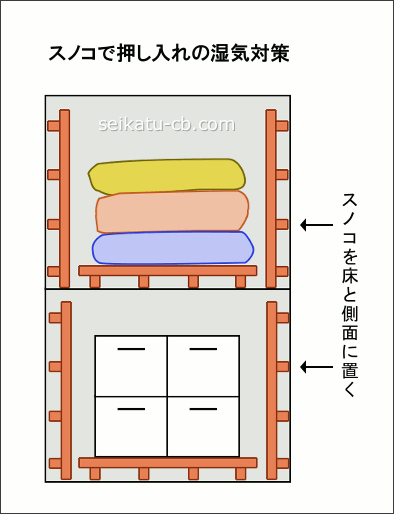
新聞紙で湿気取り
丸めた新聞紙を置く
押し入れの中の湿気、悩みの種ですよね。そんなときに手軽にできて効果的なのが新聞紙の活用です。使い方は新聞紙を丸めておくだけです。新聞紙は新しいものだとインクが付くことがあるので古いものを使います。おき場所は通風のために押し入れの下に敷いたスノコの間でもいいですし、どこか開いた場所でもかまいません。スノコは間に詰めすぎると今度は通風が悪くなるので注意してください。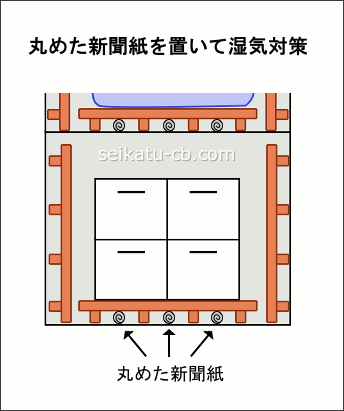
丸めた新聞紙をつなぎ合わせて吊るす
丸めた新聞紙をいくつか用意して端を紐でつなぎ合わせ、すだれのような状態にしてつるしておくといった方法もあります。針金ハンガーがあると以下の画像のようにその下に新聞紙を吊るすことで掛けやすくなって便利です。新聞紙を吊るす数は押し入れの空いたスペースに応じて3でも4つでもいいです。新聞も除湿剤と同じで吸湿力いっぱいになってしおれてくればそれ以上の効果は期待できませんので、時々の点検と交換を忘れずに!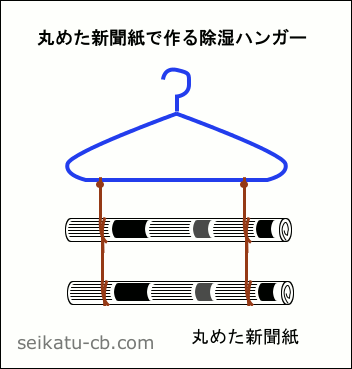
乾燥剤・除湿剤は交換時期を忘れずに!
除湿剤は奥のすみに置く
押入れの中の除湿で定番なのがやはり乾燥剤、除湿剤でしょう。吸収力いっぱいになったらそれ以上は除湿効果がまったくなくなるので、おいたらおきっぱなしにならないよう時々点検して、交換するようにしましょう。湿気は奥のほうにたまりやすいのでなるべく除湿剤などは奥におくようにしましょう。その際確保した空気の通り道をふさがないように注意しましょう。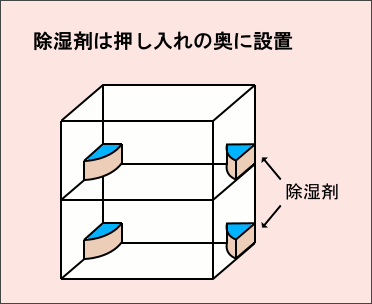
除湿剤は交換時期に注意
除湿剤は集めた湿気を下のタンクの部分にためていきます。タンクは半透明になっているので外からでもどのくらい水が溜まっているのかはすぐに確認できます。この部分が満タン近くになるともう吸湿できないので、その時は交換しましょう。除湿剤には備長炭などが使われることが多く、除湿効果だけでなく押し入れの消臭効果も期待できます。|
PR 備長炭ドライペット 除湿剤 使い捨てタイプ (420ml×3個パック)×3個備長炭ドライペット amazonで購入 楽天市場で購入 |
スノコが邪魔で置けない時
空気の通り道を作るためにスノコを側面にも置くといいと紹介しましたが、さらにさらに市販の乾燥剤も利用した場合は、置く場所に困ることもあります。乾燥剤は奥のすみに置くのよいのですが、スノコがあるとさらに内側に置く必要があります。こうなると収納スペースもだいぶ狭くなるので、その場合はスノコは側面にはおかず、スノコ分のスペースを空けて収納し、奥に乾燥剤を設置するといいです。収納ケースの中にも乾燥剤を
湿気は押し入れの中だけでなくしまっている収納ケースの中にもこもりやすいです。収納ケースの中の衣類が傷まないよう、ケースの中には乾燥剤を入れておくといいです。キャスターを敷く
下にはスノコの変わりにキャスター付きの台を置いてもいいです。キャスターもスノコと同様床との間に隙間が出来るので空気の流れを確保でき、さらにキャスターが付いているので収納物を出し入れしやすくて便利です。
ものを詰め込みすぎない
押入れは特に湿気がこもりやすい場所です。そのため隙間を確保して通風を意識することが大切になります。押入れの中がものでいっぱいで隙間なくぎゅうぎゅうなのはもってのほかです。整理整頓して詰め込みすぎないようにしましょう。また奥の隙間も大事ですので、壁に密着するほど押し込まないで5cm以上は隙間を確保するようにしましょう。
湿気は下にいくほど高い
湿気は下に行くほど高くなります。上段、下段とわかれた押入れならなるべくなら上段には湿気に弱いもの、下段には湿気に強いものを置きましょう。
毎日使う布団、特に敷布団の場合、汗など水分がしみこんでいるので、押入れの中に湿気を持ち込んでしまいます。したがって布団類は上段にしまうようにしましょう。布団の量が多くて下段にもしまわなければ仕方がない場合はやむおえませんが、その場合でもしまう前にまずは布団を広げ、ある程度そのままにして水分を発散させるなどし、中に湿気を持ち込まないよう工夫しましょう。
毎日使う布団、特に敷布団の場合、汗など水分がしみこんでいるので、押入れの中に湿気を持ち込んでしまいます。したがって布団類は上段にしまうようにしましょう。布団の量が多くて下段にもしまわなければ仕方がない場合はやむおえませんが、その場合でもしまう前にまずは布団を広げ、ある程度そのままにして水分を発散させるなどし、中に湿気を持ち込まないよう工夫しましょう。
布団はしばらくそのまま
布団は乾燥させてから収納
布団はたたんで押入れにしまいますが、寝ているときも人間は汗をかいています。その汗がしみこんだ布団を押入れにそのまましまうと、少なからず湿気の原因となります。押入れに入れる際は、1時間ほど時間を空けて汗が発散したかなといったころあいで、たたんでしまうようにしましょう。それから定期的に布団を干すことも忘れずに!一晩でコップ1杯分の汗をかく
健康な大人なら一晩でコップ一杯分の寝汗をかくといわれています。書いた寝汗は掛布団に30%、敷布団に70%吸収されるといいます。これだけの水分を含んだ布団をすぐに押し入れに入れてしまっては押し入れの湿度の上昇につながってしまいます。まずはしっかりと乾燥させてからいれるようにしましょう。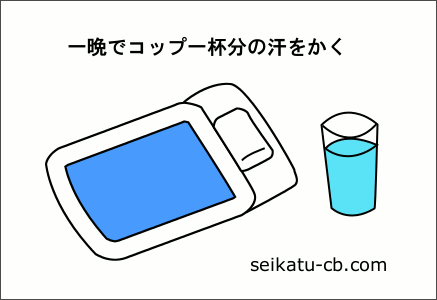
押入れの換気
押入れは閉めっぱなしにしていると湿気がこもります。ふすまを開けて換気に気をつけましょう。このさい片側一方だけを大きく開けるよりも、ふすまを中央に寄せ、両側空けるようにすると空気の流れができて換気効果がぐんと上がります。空気の循環が悪いときは片側から扇風機で風を当てて、空気の流れを作るのも効果的です。収納ボックスなどがある場合は、引き出しもあけておきましょう。
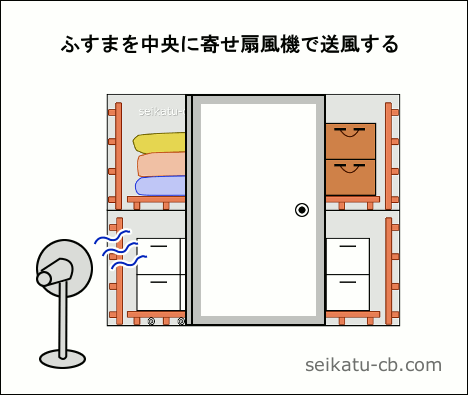
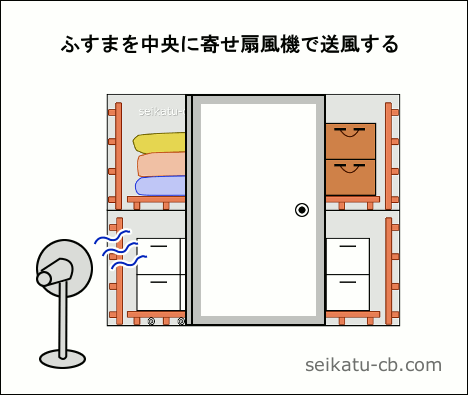
コンクリートの壁の結露には?
上記のような様々な湿気対策をとれば通常なら押入れの湿気対策は十分なのですが、押入れの壁がコンクリート作りで結露が発生しやすい環境だと、それでも十分に対策できない場合もあります。その場合はコンクリートの壁や床に断熱シートを貼って見るのもいいでしょう。
もともと空気中には一定の水分(水蒸気・水の気体)が含まれていますが、空気の温度が下がると含んでいられる水分の量も減少して行きます。空気が冷たいコンクリートと接触すると急激に冷やされ、保持できる水分の量も減少し、あふれた水分は結露となってコンクリートの壁に付着するのです。
断熱シートを貼ることで空気が直接冷たいコンクリートと接触することがなくなり結露が発生しにくくなります。断熱シートはしっかりと外周を両面テープなどで接着して使いましょう。断熱シートがない場合は引越の梱包などに使うエアキャップ(プチプチ)でも代用できます。
もともと空気中には一定の水分(水蒸気・水の気体)が含まれていますが、空気の温度が下がると含んでいられる水分の量も減少して行きます。空気が冷たいコンクリートと接触すると急激に冷やされ、保持できる水分の量も減少し、あふれた水分は結露となってコンクリートの壁に付着するのです。
断熱シートを貼ることで空気が直接冷たいコンクリートと接触することがなくなり結露が発生しにくくなります。断熱シートはしっかりと外周を両面テープなどで接着して使いましょう。断熱シートがない場合は引越の梱包などに使うエアキャップ(プチプチ)でも代用できます。
出来てしまったカビには
湿気対策をする前にすでに湿気により押し入れないに黒ずみなどのカビが出来てしまった場合は、カビ取り剤などで掃除するほかありません。乾燥した天気のいい日に押入れの中のものを取り出し、カビにカビ取り剤を添付して30分ほど待ち、後は水拭きでカビ取り剤を取り、半日ほど乾燥させて終わりです。詳しくは押入れのカビ予防と掃除の仕方をご覧ください。
まとめ
それでは最後に押入れの湿気対策について対策順にまとめていきます。まずはスノコを床に敷き、横の壁に立てかけます。こうして空気の通り道を確保したあと、ロール上に丸めた新聞紙をスノコをふさがない程度にその間に7,8箇所ほどはさみます。除湿剤がある場合は除湿剤を奥に設置します。
除湿対策をした後は収納物をしまっていきます。収納するさいは奥一杯に収納するのではなく、奥の隙間を5cm以上あけるようにして空気の通り道を確保します。収納は布団など湿気に弱いものは上段にしまい、湿気に比較的強いものは下段にしまいます。
そして定期的な押入れの換気も忘れずに。換気では押入れの両方のふすまを中央に寄せて開き、半日ほどそのままにしておきます。空気の流れが悪い場合は片側から扇風機で風を送ります。
こうした対策をしても、もしくは対策が間に合わずに押し入れの壁にカビが発生した場合は、カビ取り剤を添付してしばらく置き、水拭きでカビ取り剤をしっかりとふき取って、そのあと十分に乾燥させます。以上が湿気対策とカビが出来た際の対処法です。
除湿対策をした後は収納物をしまっていきます。収納するさいは奥一杯に収納するのではなく、奥の隙間を5cm以上あけるようにして空気の通り道を確保します。収納は布団など湿気に弱いものは上段にしまい、湿気に比較的強いものは下段にしまいます。
そして定期的な押入れの換気も忘れずに。換気では押入れの両方のふすまを中央に寄せて開き、半日ほどそのままにしておきます。空気の流れが悪い場合は片側から扇風機で風を送ります。
こうした対策をしても、もしくは対策が間に合わずに押し入れの壁にカビが発生した場合は、カビ取り剤を添付してしばらく置き、水拭きでカビ取り剤をしっかりとふき取って、そのあと十分に乾燥させます。以上が湿気対策とカビが出来た際の対処法です。
※ 参考文献
掃除・収納のきほん
決定版暮らしの裏ワザ知得メモ888
1・2・3でキレイが続く収納とお掃除一緒にレシピ
ラクラク家事の本
科学的に正しい暮らしのコツ
住まいの汚れスッキリ解消術
決定版 暮らしの裏ワザ知得メモ888
いちばんわかりやすい家事の基本大事典
掃除・収納のきほん
決定版暮らしの裏ワザ知得メモ888
1・2・3でキレイが続く収納とお掃除一緒にレシピ
ラクラク家事の本
科学的に正しい暮らしのコツ
住まいの汚れスッキリ解消術
決定版 暮らしの裏ワザ知得メモ888
いちばんわかりやすい家事の基本大事典
|
最終更新日 2018/01/18 |
 TOPへ TOPへ  住まいTOPへ 住まいTOPへ  HOMEへ HOMEへ
|
湿気編一覧
その他一覧
重なったコップの外し方
鏡が曇る原因と対策、洗面所やお風呂場の鏡を曇らせなくするには?
シールの上手な剥がし方
ガムテープ跡の取り方、はがし方
セロテープ跡の綺麗な取り方、はがし方
油性マジックの落書き
鏡が曇る原因と対策、洗面所やお風呂場の鏡を曇らせなくするには?
シールの上手な剥がし方
ガムテープ跡の取り方、はがし方
セロテープ跡の綺麗な取り方、はがし方
油性マジックの落書き
PR |
since 2002/09/28
Copyright(C)2002 生活知恵袋 All Rights Reserved
Copyright(C)2002 生活知恵袋 All Rights Reserved



